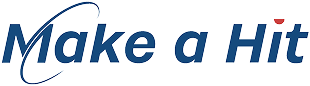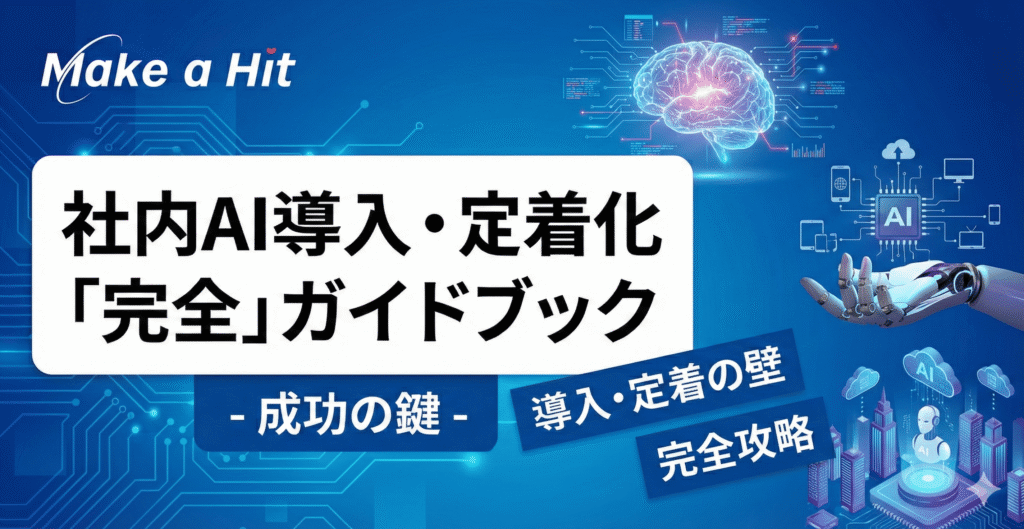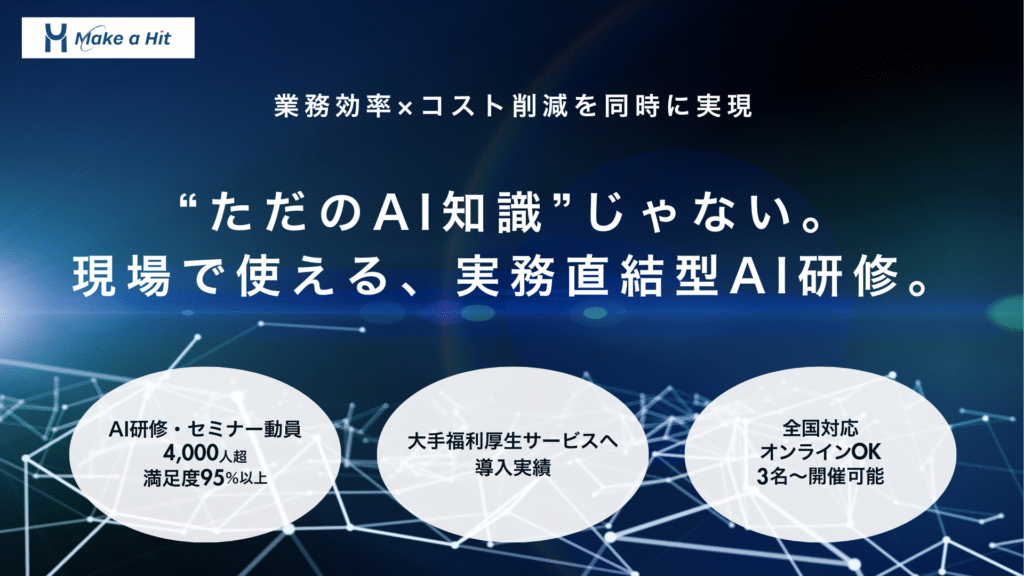「AIを活用したいけど、研修費用が高額で二の足を踏んでいる…」
「AI研修は助成金が申請できると聞いたけど、うちの会社でもできるのかな…」
多くの企業がAI導入を検討するなか、人材育成にかかるコストが大きな壁となっています。実は、国の助成金を活用すれば、AI研修費用の最大75%が支援される可能性があるのです。
厚生労働省の人材開発支援助成金をはじめ、複数の支援制度があり、たとえば中小企業なら「事業展開等リスキリング支援コース」で研修費用の75%、さらに賃金助成として1時間あたり960円も受け取れます(出典:厚生労働省「人材開発支援助成金」)。
ただし、多くの企業が申請手続きの複雑さや期限の厳しさから、せっかくの制度を活かしきれていないのが現状です。弊社では4,000人以上にAI研修を提供してきた経験から、助成金申請の成功ノウハウを蓄積しています。
この記事では、AI研修に使える助成金の種類、申請の流れ、成功のポイントを、専門家の視点からわかりやすく解説します。記事を読めば、どの助成金が自社に最適か、申請で失敗しないためのコツは何かがすぐにわかります。
少ない自己負担でAI人材を育成し、ビジネスを加速させるチャンスです。ぜひこの記事を参考に、国の支援制度を最大限に活用してください。
記事監修者

久保田 亮-株式会社メイカヒット代表
【経歴・実績】
・4,000人以上へのAI研修実績
・Gensparkアンバサダー
・マーケターとしての取引企業200社以上
・マーケティング/広報顧問累計6社
・自社メディアでの販売実績10億円以上
・Webスクールメイカラ主宰
田中 凌平-株式会社メイカヒット代表
【経歴・実績】
・Notta公式アンバサダー
・AIを活用し生産性300%向上
・日本インタビュー協会認定インタビュアー
・年間150名以上の取材実績
・ラグジュアリーブランドで5年勤務

人材開発支援助成金とは?基本知識をかんたん解説
人材開発支援助成金は、企業がおこなう従業員の研修費用を国が支援する制度です。AI研修のような専門的な訓練にかかる費用の一部を、国が助成金として支給してくれます。たとえば、中小企業なら研修費用の最大75%まで補助を受けられるため、多くの企業が活用しています。
弊社は4,000人以上にAI研修を提供してきた経験から、この助成金の活用が企業の人材育成コストを大幅に削減できることを実感しています。実際に、適切な申請手続きをおこなうことで、実質的な企業負担を25〜30%程度まで抑えられるケースが多くあります。
厚生労働省の公式サイトによると、この制度は「事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度」と定義されています(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html)
つまり、AI研修のような専門性の高い訓練を実施する企業にとって、とても役立つ支援制度といえます。ただし、申請には一定の手続きが必要なため、正しい知識を身につけることが重要です。
人材開発支援助成金の仕組み|国から研修費用を支援してもらえる制度
人材開発支援助成金の仕組みは、企業が従業員の能力開発に投資する際の経済的負担を軽減するものです。具体的には、研修にかかる経費(講師料、教材費など)と研修期間中の賃金の一部を助成します。
助成対象となる費用は大きく2つに分かれます。ひとつは経費助成で、外部講師への謝金や研修で使用する教材費、会場費などが含まれます。もうひとつは賃金助成で、研修を受講している従業員の給与の一部が支給されます。
弊社のAI研修を受講したクライアント企業の例では、3日間の研修(1人あたり30万円)に対して、中小企業なら経費の75%にあたる22.5万円が助成されました。さらに賃金助成として1時間あたり960円が支給され、トータルで大幅な費用軽減につながっています(※2025年5月現在)。
助成金を利用できる事業主の要件
助成金を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず大前提として、雇用保険の適用事業所であることが必須条件です。つまり、従業員を雇用し、雇用保険に加入している企業が対象となります。
さらに、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成する必要があります。これは、計画的に人材育成をおこなう体制が整っていることを示すためのものです。
弊社が研修を提供してきた企業では、従業員10名程度の小規模事業者から、数千名規模の大企業まで、幅広く助成金を活用されています。重要なのは、訓練期間中も従業員に賃金を適正に支払っていることや、労働関係法令を遵守していることです。
これらの要件は一見複雑に見えますが、通常の事業運営をおこなっている企業であれば、多くの場合クリアできる内容となっています。
中小企業事業主と中小企業以外の事業主の助成率の違い
助成率は企業規模によって異なり、中小企業の方が手厚い支援を受けられる仕組みになっています。厚生労働省の公式リーフレットによると、事業展開等リスキリング支援コースの場合、中小企業は経費の75%、大企業は60%が助成されます(出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001469154.pdf)
賃金助成についても差があり、中小企業は1時間あたり960円、大企業は480円となっています。たとえば、5日間(40時間)の研修を実施した場合、中小企業なら従業員1人あたり38,400円の賃金助成を受けられます。
この差は、資金力に限りがある中小企業の人材育成を特に支援する目的で設定されています。わたしたちのクライアント企業でも、中小企業の方が助成金活用に積極的な傾向が見られます。
なお、中小企業の定義は業種によって異なりますが、たとえばサービス業なら資本金5,000万円以下または従業員100人以下の企業が該当します。
AI研修で人材開発支援助成金を活用するメリット
AI研修に助成金を活用する最大のメリットは、質の高い研修を低コストで実施できることです。わたしたちの経験では、助成金を上手に活用することで、実質的な企業負担を大幅に軽減できます。
また、助成金申請のプロセスを通じて、体系的な研修計画を立てる必要があるため、場当たり的ではない戦略的な人材育成が可能になります。申請書類の作成過程で、なぜAI研修が必要なのか、どのような効果を期待するのかを明確にすることで、研修の目的意識も高まります。
さらに、助成金の対象となる研修は一定の品質基準を満たす必要があるため、質の高い研修プログラムを選択する動機付けにもなります。わたしたちのAI研修も、助成金の要件を満たすよう設計されており、実践的なスキル習得を重視しています。
実際に助成金を活用して研修を受講した企業からは、「想像以上にコストを抑えられた」「社内の理解も得やすかった」といった声をいただいています。
【2025年版】AI研修で使える3つの助成金コース
人材開発支援助成金には複数のコースがあり、それぞれ対象となる研修や助成内容が異なります。AI研修で特に活用しやすい3つのコースについて、2025年5月現在の最新情報をもとに解説します。
弊社が4,000人以上に提供してきたAI研修の経験から、各コースの特徴と活用のポイントをお伝えします。適切なコースを選択することで、より効果的な助成金活用が可能になります。
厚生労働省の公式サイトでは、7つのコースが紹介されていますが、AI研修に特に適しているのは「事業展開等リスキリング支援コース」「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」の3つです(参照:厚生労働省 人材開発支援助成金ページ)
これらのコースは、それぞれ異なる目的や対象者に応じて設計されているため、自社の状況に最適なコースを選ぶことが重要です。
事業展開等リスキリング支援コース
事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立ち上げやDX推進にともなう人材育成を支援するコースです。AI導入による業務改革や新サービス開発を目指す企業に最適な制度といえます。
このコースの特徴は、既存事業の延長ではなく、新たな分野への進出や事業展開を支援する点にあります。たとえば、製造業がAIを活用した予知保全サービスを開始する場合や、小売業がAIチャットボットによる顧客対応を導入する場合などが対象となります。
弊社のクライアント企業では、このコースを活用してAI戦略立案研修や生成AI実践研修を実施し、新規事業の基盤づくりに成功した事例が多数あります。助成率も他のコースと比較して高く設定されているため、積極的な活用をおすすめします。
厚生労働省が公表している助成率(中小企業75%、大企業60%)
厚生労働省の公式資料によると、事業展開等リスキリング支援コースの経費助成率は、中小企業75%、大企業60%と設定されています(出典:厚生労働省「人材開発支援助成金に事業展開等リスキリング支援コースを創設しました」https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001070651.pdf)。これは他のコースと比べても高い助成率です。
賃金助成についても、中小企業は1時間あたり960円、大企業は480円が支給されます。たとえば、5日間(40時間)の研修を実施した場合、中小企業なら従業員1人あたり38,400円の賃金助成を受けられる計算になります。
弊社の研修を受講された企業の実例では、研修費用30万円に対して中小企業で22.5万円(75%)の経費助成を受け、さらに賃金助成を含めると実質的な負担が大幅に軽減されました。
この高い助成率は、企業の新たな挑戦を後押しするために設定されており、AI導入による事業革新を目指す企業にとって大きなチャンスといえます。
対象となるAI研修の具体例
対象となるAI研修は、事業展開や新規事業に直結する内容である必要があります。弊社の研修プログラムから、実際に助成金の対象として認められた具体例をご紹介します。
まず、生成AIを活用した業務効率化研修があります。ChatGPTやClaudeを使った実践的な業務改善手法を学ぶ内容で、新たなサービス開発や業務プロセスの革新につながります。また、AI画像認識技術を用いた品質管理システム構築研修も対象となっています。
さらに、AIマーケティング戦略立案研修や、機械学習モデルの開発・実装研修なども該当します。重要なのは、単なるツールの使い方ではなく、具体的な事業展開にどう活かすかという視点を含めることです。
弊社では、各企業の事業計画に合わせて研修内容をカスタマイズし、助成金の要件を満たすようサポートしています。
OFF-JT(Off the Job Training)の要件
OFF-JT(職場外訓練)として認められるためには、通常の業務と明確に区別して実施する必要があります。つまり、日常業務をしながらの研修ではなく、専用の時間を設けて学習に集中できる環境が求められます。
具体的な要件として、実訓練時間が10時間以上であること、業務命令により受講すること、事業主が訓練費用を全額負担することなどがあります。また、専門の講師による体系的なカリキュラムが必要です。
弊社のAI研修では、これらの要件を満たすため、2日間(16時間)の集中研修形式や、週1回×10週間(計20時間)の連続研修形式などを提供しています。研修場所も業務スペースとは別の会議室やオンライン環境を使用し、OFF-JTの要件を確実にクリアします。
研修実施時は出欠管理も重要で、弊社では専用の管理システムを導入し、記録を確実に残す体制を整えています。
人材育成支援コース
人材育成支援コースは、幅広い従業員を対象に職務に必要な知識・技能を習得させる研修を支援するコースです。AI基礎研修や部署全体でのAIリテラシー向上研修など、組織全体の底上げを図る際に適しています。
このコースの特徴は、正社員だけでなく、契約社員やパートタイマーも対象となる点です。AIは特定の専門職だけでなく、あらゆる職種で活用できるツールであるため、全社的な教育に最適な制度といえます。
弊社の研修実績では、営業部門、管理部門、製造部門など、さまざまな部署の方々が受講され、それぞれの業務に応じたAI活用スキルを習得されています。基礎から応用まで段階的に学べるカリキュラムを用意しているため、初心者でも安心して受講いただけます。
対象となる労働者(被保険者)
対象となるのは、雇用保険の被保険者全般です。正社員はもちろん、契約社員(有期雇用労働者)、パートタイマー(週20時間以上勤務)、派遣社員(派遣元で申請)も含まれます。
この幅広い対象設定により、企業は柔軟な人材育成計画を立てることができます。たとえば、まず管理職にAI基礎研修を実施し、その後一般社員へ展開するといった段階的なアプローチも可能です。
弊社のクライアント企業では、パート社員も含めた全社員研修を実施し、組織全体のAIリテラシー向上に成功した事例があります。特に小売業や飲食業など、多様な雇用形態の従業員が働く業界で好評をいただいています。
ただし、役員や事業主は対象外となるため、申請時には注意が必要です。
職務関連訓練として認められる研修内容
職務関連訓練として認められるためには、現在または将来の職務に必要な知識・技能を習得する内容である必要があります。AI研修においては、業務との関連性を明確に示すことが重要です。
たとえば、営業部門向けには「AIを活用した顧客分析と提案力向上研修」、管理部門向けには「AIツールによる業務効率化と生産性向上研修」といった具合に、職務に直結したタイトルと内容設計が必要です。
弊社では、受講者の業務内容に応じてカスタマイズした演習を取り入れ、学んだスキルを即座に実務で活用できるよう工夫しています。実際の業務データを使った分析演習や、業務フローの改善提案作成など、実践的な内容が評価されています。
単なる教養としてのAI講座では助成対象とならないため、職務との関連性を計画段階から明確にすることが大切です。
実訓練時間10時間以上の要件
人材育成支援コースでも、実訓練時間が10時間以上という要件があります。これは一定の学習効果を確保するための最低基準として設定されており、しっかりとした研修内容が求められます。
弊社の経験では、AI研修で実践的なスキルを身につけるには最低でも20時間程度は必要です。そのため、3日間集中コース(24時間)、週1回×8週間コース(32時間)、月2回×3か月コース(24時間)などのプログラムを提供しています。
研修時間の計算では、休憩時間や自習時間は含まれません。実際に講師による指導がおこなわれる時間のみがカウントされるため、余裕をもった時間設定が必要です。
また、eラーニングを活用する場合は、標準学習時間の8割が実訓練時間として認められるなど、形式によって計算方法が異なる点にも注意が必要です。
人への投資促進コース
人への投資促進コースは、デジタル人材育成に特化した支援をおこなうコースです。高度なAIスキルを持つ人材の育成や、従業員の自発的な学習を促進する取り組みを支援します。
2023年から生成AI関連の研修も明確に対象となり、ChatGPTやClaudeなどの高度な活用方法も助成対象として認められるようになりました。弊社のクライアント企業でも、このコースを活用した高度AI人材の育成が増えています。
このコースの特徴は、定額制の学習サービス(サブスクリプション型)も対象となる点です。従業員が自由に学習できる環境を整備し、継続的なスキルアップを支援することができます。
デジタル人材育成の専門的知識・技能
デジタル人材育成として認められる研修内容は、より高度な専門性が求められます。機械学習エンジニア育成研修、データサイエンティスト養成講座、AIプロジェクトマネジメント研修などが該当します。
特に注目すべきは、生成AI関連のスキルも専門的知識として認められるようになった点です。高度なプロンプトエンジニアリング、AIを活用したコンテンツ制作、LLM(大規模言語モデル)のファインチューニングなども対象となります。
弊社の「AIエンジニア養成コース」では、Pythonプログラミングから機械学習モデルの構築、実装までを体系的に学びます。また、「生成AI実践マスター講座」では、ChatGPT APIの活用やカスタムGPTの開発など、より実践的なスキルを習得できます。
これらの高度な研修は、企業のAI戦略を推進する中核人材の育成に不可欠です。
定額制訓練(サブスクリプション型)も対象
人への投資促進コースの大きな特徴として、定額制の訓練サービス(サブスクリプション型)も助成対象となる点があります。これにより、従業員が自由に学習できる環境を整備しやすくなりました。
対象となるサービスの例として、AIやプログラミングのオンライン学習プラットフォーム、定額制のeラーニングサービス、月額制のAI実践トレーニングプログラムなどがあります。
弊社でも、企業向けに「AI学習プラットフォーム」を提供しており、従業員が自分のペースで学習を進められる環境を整備しています。動画講座、演習問題、実践課題などを組み合わせ、効果的な学習を支援します。
定額制サービスの活用により、従業員の学習意欲に応じた柔軟な人材育成が可能となり、継続的なスキルアップを実現できます。
他コースとの支給対象訓練の違い
人への投資促進コースは、他のコースと比較していくつかの特徴があります。まず、より高度な専門性を持つ訓練が対象となり、デジタル分野での先端スキル習得を重視しています。
また、従業員の自発的な学習を支援する仕組みも含まれており、定額制サービスの活用が可能な点も大きな違いです。さらに、海外の教育機関での研修も一定の条件下で対象となるなど、グローバルな視点での人材育成も視野に入れています。
弊社の研修プログラムでは、このコースの特性を活かし、AIプロフェッショナル人材の育成に注力しています。単なる知識習得にとどまらず、実践的なプロジェクト経験を通じて、即戦力となる人材を育成します。
企業の中長期的なAI戦略を支える人材育成には、このコースの活用が最適といえるでしょう。
職業訓練実施計画届の提出から支給申請まで
助成金を受けるためには、適切な手続きを踏む必要があります。弊社が4,000人以上に研修を提供してきた経験から、申請手続きのポイントをお伝えします。期限の厳守と書類の正確さが何よりも重要です。
多くの企業が申請手続きを難しく感じていますが、実際には必要書類を順番に準備すれば問題ありません。ポイントは計画的に進めることと期限を守ることです。厚生労働省の公式サイトでも手続きの流れが紹介されていますので、参考にしてください(出典:厚生労働省「人材開発支援助成金」)
申請から支給までの流れを、弊社のサポート経験をもとにわかりやすく解説します。
ステップ1:職業能力開発推進者の選任と事前準備
最初に行うべきは、職業能力開発推進者の選任です。この推進者は社内の人材育成を統括する役割を担います。多くの場合、人事部門や総務部門の管理職が選任されています。
推進者選任後は、以下の準備を進めます。
- 事業内職業能力開発計画の策定
- 研修の目的と期待される効果の明確化
- 対象従業員の選定
弊社のクライアント企業では、この段階で研修内容についてご相談いただくことが多いです。AI研修の具体的なカリキュラムや、助成金の対象となる内容について、専門的なアドバイスを提供しています。
特に重要なのは、研修が「なぜ必要か」という目的を明確にすることです。単に「AIが話題だから」ではなく、「業務効率化のために必要」など、具体的な理由付けが求められます。
ステップ2:職業訓練実施計画届の提出(訓練開始日の1ヶ月前まで)
職業訓練実施計画届は、訓練開始日の1ヶ月前までに労働局に提出する必要があります。この「1ヶ月前」という期限は絶対で、1日でも遅れると助成金の対象外となってしまいます。
- 訓練の内容と時間数
- 対象となる従業員の人数と属性
- 訓練期間と実施スケジュール ・訓練にかかる費用の見積もり
弊社では研修を提供する際、この計画届の作成に必要な情報(カリキュラム詳細、時間配分、費用内訳など)を整理してお渡しします。これにより、企業様の書類作成の負担を軽減しています。
提出先は各都道府県労働局ですが、管轄のハローワークを経由して提出することも可能です。不明点があれば事前に労働局に問い合わせることをおすすめします。
ステップ3:計画に沿った訓練の実施
計画が承認されたら、実際の訓練を実施します。重要なのは、提出した計画どおりに訓練を行うことです。計画と実際の内容が大きく異なると、助成金が支給されない可能性があります。
- 出欠管理を確実に行う
- 訓練日誌や実施記録を作成する
- 計画変更が必要な場合は事前に届け出る
弊社のAI研修では、出欠管理システムを導入し、自動的に記録が残る仕組みを整えています。また、研修の様子を写真で記録するなど、実施の証拠となる資料作成もサポートしています。
訓練中は受講者の理解度を確認しながら進めることも重要です。単に座学を受けるだけでなく、演習や質疑応答を通じて実践的なスキルを身につけられるよう工夫することで、より効果的な人材育成が可能になります。
ステップ4:支給申請書の提出(訓練終了日の翌日から2ヶ月以内)
訓練が終了したら、2ヶ月以内に支給申請書を提出します。この期限も厳格で、遅れると助成金を受けられなくなります。
- 支給申請書(様式第5号など)
- 訓練実施状況報告書
- 出勤簿、賃金台帳の写し
- 訓練にかかった経費の領収書
弊社は研修終了後、速やかに必要書類(修了証明書、実施報告書など)を発行し、申請手続きをサポートしています。経験上、書類の不備が最も多い失敗原因ですので、チェックリストを用いた確認をおすすめします。
支給申請書類に不備があると再提出を求められ、支給までの期間が長くなります。書類作成時には特に金額計算や日付に注意が必要です。
支給・不支給決定までの期間
支給申請書を提出してから、実際に助成金が支給されるまでには一定の期間がかかります。標準的な処理期間は申請から2〜3ヶ月程度です(※2025年5月現在)。
この期間は申請の混雑状況や書類の不備の有無によって変動します。弊社のクライアント企業の事例では、書類に不備がない場合は2ヶ月程度で支給決定通知が届くケースが多いです。
- 申請書類の受理(労働局)
- 書類審査(1〜2か月)
- 必要に応じて追加資料の要求
- 支給・不支給の決定
- 支給決定通知書の送付
- 指定口座への振込
この期間中、労働局から問い合わせがある場合もあるため、連絡がつく体制を整えておくことが重要です。特に書類の不備について確認されることが多いので、提出した書類のコピーは必ず保管しておきましょう。
助成金申請の成功事例と注意点
助成金申請で成功するためのポイントは「計画性」と「正確性」です。弊社が4,000人以上のAI研修を提供する中で、多くの企業の申請をサポートしてきた経験から、成功事例と注意点をお伝えします。
事前に手続きのポイントを押さえておくことで、スムーズな申請が可能になります。特に書類の不備による不支給は非常に多いため、細心の注意が必要です。ほとんどの失敗は基本的なルールの見落としから発生しています。
4,000人の研修実績から見えた申請成功のポイント
弊社の経験から、助成金申請が成功する企業には共通点があります。それは「計画性」と「正確性」、そして「目的の明確さ」です。
- 余裕をもったスケジュール設定(申請期限の2週間前には書類を完成)
- 研修内容と事業計画の整合性(なぜAI研修が必要なのかを明確に)
- 正確な書類作成(記載ミスや添付漏れがない)
- 適切な研修時間と内容(10時間以上の実践的カリキュラム)
特に重要なのは、研修の必要性を論理的に説明できることです。単に「AIが話題だから」ではなく、「業務効率化のためにAIツールの導入が必要で、そのための人材育成が不可欠」といった具体的な理由付けが求められます。
弊社のサポートでは、申請前に企業の課題や目標をヒアリングし、それに合わせた研修プランと申請書類の作成をお手伝いしています。この事前準備が申請成功の大きな鍵となっています。
支給対象となる訓練と対象外となる訓練の違い
助成金の対象となる訓練には明確な基準があります。AI研修においても、この基準を満たす必要があります。
- 職務に直接関連する内容であること
- 体系的なカリキュラムが組まれていること
- 専門的な知識
- 技能の習得が目的であること
- 業務命令による受講であること
- 趣味や教養としてのAI講座
- 自己啓発目的の研修
- 業務との関連性が薄い内容
- 職業倫理など一般的な内容のみの研修
弊社のAI研修は、実務での活用を前提に設計されているため、助成金の対象として認められやすい特徴があります。たとえば「ChatGPTを使った業務効率化研修」では、実際の業務フローの改善案作成まで行います。
研修内容を検討する際は、単なる知識習得ではなく、具体的な業務改善や新規事業創出につながる内容設計が重要です。これにより、助成金の対象となるだけでなく、研修効果も高まります。
よくある申請書類の不備と対策
申請書類の不備は、助成金不支給の最も多い原因です。弊社がこれまでに見てきた典型的な不備とその対策をご紹介します。
- 計算ミス(訓練時間数、助成金額の計算)
- 添付書類の漏れ(特に賃金台帳や出勤簿)
- 記載内容の矛盾(計画と実績の不一致)
- 押印漏れや日付の誤り
対策としては、以下のチェックリストの活用をおすすめします。
- 全ての必要書類が揃っているか
- 数字の計算は複数人でチェックしたか
- 記載内容に矛盾はないか
- 提出期限まで余裕はあるか
弊社は研修提供者として、必要書類のテンプレートや記載例を提供し、企業様の書類作成をサポートしています。特に初めて申請される企業様には、丁寧なアドバイスを心がけています。
また、過去の不備事例をもとにしたチェックポイント集も用意していますので、申請前の最終確認にご活用ください。このように、事前の準備と確認を徹底することで、不支給リスクを大幅に減らすことができます。
助成対象となるAI研修の設計方法
助成金の対象となるAI研修を設計するには、いくつか重要なポイントがあります。弊社の豊富な研修設計経験から、効果的なカリキュラム作りの秘訣をご紹介します。
助成金の要件を満たすだけでなく、実際の業務で成果が出る研修内容を目指すことが大切です。形式的な研修では、せっかくの投資が無駄になってしまいます。弊社の4,000人以上のAI研修実績をもとに、助成対象となる効果的な研修設計の方法をお伝えします。
OFF-JTとして認められる訓練の要件
OFF-JT(Off the Job Training:職場外訓練)として認められるためには、通常業務と明確に区別された訓練である必要があります。具体的には以下の要件を満たすことが求められます。
- 所定労働時間内に実施される(または時間外手当が支給される)
- 通常の生産活動と区別して行われる
- 専門の講師または指導員が配置される
- 訓練のための場所が確保されている
弊社のAI研修では、専用の研修室やオンライン環境を使用し、業務から完全に離れて学習に集中できる環境を提供しています。また、AI専門の講師が体系的なカリキュラムに基づいて指導を行うため、OFF-JTの要件を確実に満たします。
厚生労働省の指針では、「業務命令によって、労働時間中または訓練のための特別な時間を設けて行われる訓練」とされています。日常業務の中で行われるOJT(On the Job Training)は助成対象外となる点に注意が必要です。
階層別の訓練カリキュラム例
AI研修は、受講者の役職や担当業務によって内容を変える必要があります。弊社では階層別に最適化されたカリキュラムを提供しています。
それぞれの階層で必要とされるAIスキルは異なるため、画一的な研修では効果が限定的です。役職や業務内容に応じた研修設計が、助成金申請の際にも評価されるポイントとなります。
経営層向け:AI活用戦略の専門的知識
経営層向けの研修では、AIを経営戦略にどう組み込むかという視点が重要です。技術的な詳細よりも、ビジネスインパクトや投資対効果に焦点を当てます。
- AI技術の最新動向と市場予測(3時間)
- 自社事業へのAI適用可能性分析(4時間)
- AI導入のリスクと法的課題(3時間)
- AI戦略立案ワークショップ(6時間)
実際にこの研修を受講された経営者の方々からは、「AIに対する漠然とした不安が、具体的な戦略に変わった」という声をいただいています。助成金を活用することで、経営層の意識改革も進めやすくなります。
弊社の経験では、経営層が正しくAIを理解することで、全社的な活用が加速します。また、助成金申請においても、経営層の理解と支援があると、スムーズに進むケースが多いです。
一般従業員向け:職務に関連したAI活用技能
一般従業員向けには、日常業務で即座に活用できるAIツールの使い方を中心に研修を設計します。実践的なスキル習得に重点を置いています。
- AI・生成AIの基礎知識(4時間)
- ChatGPT/Claudeの実践活用法(8時間)
- 業務効率化のためのプロンプト作成(6時間)
- 部署別AI活用事例と演習(6時間)
弊社の研修では、受講者の実際の業務課題を題材にした演習を多く取り入れています。これにより、研修終了後すぐに業務改善に着手できる即戦力を育成します。
受講者からは「明日から使える具体的なスキルが身についた」「研修直後から業務時間が30%削減できた」といった声をいただいています。このような実践的な成果が得られる研修は、助成金の審査でも高く評価されやすい傾向にあります。
IT技術者向け:AI開発・実装の専門的技能
IT技術者向けには、より専門的なAI開発スキルの習得を目指します。プログラミングや機械学習の基礎知識がある方を対象とした高度な内容です。
- Python/機械学習ライブラリの基礎(8時間)
- ディープラーニングフレームワーク実践(12時間)
- 自然言語処理とLLMの活用(10時間)
- AIモデルの開発・評価・デプロイ(10時間)
この研修は人への投資促進コースの対象となることが多く、高度なデジタル人材育成として助成金を活用できます。受講後は社内のAIプロジェクトをリードできる人材に成長します。
弊社の研修を受講されたIT技術者からは、「理論だけでなく実践的なスキルが身についた」「自社のデータを活用したAI開発ができるようになった」といった高い評価が多いです。専門性の高い研修ほど、経費助成額も大きくなるため、計画的な活用をおすすめします。
人材開発支援助成金で失敗しないための注意点
助成金申請で失敗すると、せっかくの研修投資が無駄になってしまうリスクがあります。弊社がサポートしてきた数多くの申請事例から、絶対に避けるべきポイントをお伝えします。これらの注意点を事前に理解し、適切な対策を講じることで、助成金を確実に受給できる可能性が高まります。
厚生労働省のデータによると、不支給となる申請の多くは基本的なルールの見落としが原因です(出典:厚生労働省「人材開発支援助成金ガイドブック」)。弊社の4,000人以上のAI研修実績からも、同様の傾向が見られます。
訓練実施前の計画届提出は必須(事後申請は不可)
最も多い失敗事例が、研修を実施してから助成金申請をしようとするケースです。人材開発支援助成金は事前申請が絶対条件で、事後申請は一切認められません。
- 研修の見積もりを取ってすぐに実施してしまう
- 急な研修ニーズに対応して先に実施する
- 計画届の承認を待たずに研修を開始する
正しい手順は、計画届を提出し、労働局から受理通知を受け取ってから研修を開始することです。弊社では研修の打ち合わせ段階で、必ずこの点を確認し、適切なスケジュールをご提案しています。
実際に弊社のクライアント企業で、「すぐにでも研修を始めたい」と計画届提出前に研修を開始してしまい、助成金を受けられなかった事例があります。研修自体は好評でしたが、コスト面で大きな損失となってしまいました。
所定労働時間内の訓練でないと賃金助成対象外
賃金助成を受けるためには、研修が所定労働時間内に実施される必要があります。時間外や休日の研修では、賃金助成が受けられません。
- 平日の就業時間内(9:00〜18:00など)に実施
- 時間外研修でも残業手当を支給している場合
- 土日の自主参加型研修
- 就業時間後の任意参加研修
- 残業手当なしの時間外研修
弊社の研修では、企業様の就業規則を確認し、賃金助成が受けられる形での実施をご提案しています。多くの場合、平日の業務時間内での実施が最も効果的です。
企業の人事担当者からは「土日なら参加しやすい」という声もありますが、賃金助成を考慮すると平日実施の方がコスト効率は優れています。状況に応じた最適な実施計画を一緒に考えましょう。
訓練期間中の解雇等は支給要件違反
研修期間中および研修終了後の一定期間、受講者を解雇したり退職勧奨を行うと、助成金の支給要件違反となります。これは見落としがちな重要なポイントです。
- 研修期間中の解雇(自己都合退職は除く)
- 研修期間中の退職勧奨
- 研修終了後6か月以内の会社都合解雇
この要件は、助成金が雇用の安定を目的としているためです。弊社は研修実施前に、この点についても企業様に説明し、適切な受講者選定をサポートしています。
特に注意が必要なのは、研修と並行して組織再編や人員削減を計画している場合です。そのような場合は、実施時期や対象者を慎重に検討する必要があります。助成金申請を検討されている企業様には、人事計画と研修計画の整合性を確認することをおすすめします。
計画と実施内容の相違は不支給の原因
提出した計画と実際の研修内容が大きく異なると、助成金が不支給となる可能性があります。やむを得ず変更が必要な場合は、事前の変更届が必要です。
- 計画した講師と実際の講師が異なる
- 研修時間数の増減
- カリキュラム内容の大幅な変更
- 受講者数の変更
弊社は研修実施前に詳細なカリキュラムを作成し、計画どおりの実施を心がけています。万が一変更が必要な場合は、速やかに企業様にご連絡し、適切な手続きをサポートします。
変更が生じた際の対応例として弊社のクライアント企業では、講師の急病により代理講師が担当することになった際、事前に変更届を提出し問題なく助成金を受給できた事例があります。重要なのは、変更が生じた際の素早い対応と適切な手続きです。
申請期限の厳守(期限後の申請は受理されない)
助成金申請には厳格な期限があり、1日でも遅れると受理されません。特に支給申請は、訓練終了日の翌日から2ヶ月以内という期限があります。
- カレンダーに期限を明記する
- 期限の2週間前を社内締切とする
- 書類作成の担当者を明確にする
- 郵送の場合は配達日数も考慮する
弊社は研修終了後、速やかに必要書類を提供し、企業様の申請手続きをサポートしています。申請期限の管理は助成金受給の生命線といえます。
実際に弊社のサポートでは、研修終了日をカレンダーに登録し、終了後1ヶ月、1ヶ月半、1週間前といった具合に申請期限の確認連絡を入れるようにしています。こうした地道な管理が、確実な助成金受給につながっています。
AI研修に使える他の支援制度も要チェック
人材開発支援助成金以外にも、AI研修や導入に活用できる支援制度があります。複数の制度を組み合わせることで、より効率的な人材育成と設備投資が可能になります。特に中小企業向けの支援は手厚く設計されており、積極的な活用をおすすめします。
弊社がサポートしてきたクライアント企業の中には、複数の支援制度を上手に活用し、包括的なAI導入を実現した事例が多くあります。それぞれの制度の特徴を理解し、最適な組み合わせを検討しましょう。AI人材育成の専門家として、活用しやすい制度を厳選してご紹介します。
IT導入補助金でAIツール導入と研修をセットで申請
IT導入補助金は、中小企業のデジタル化を支援する制度です。AIツールの導入費用だけでなく、そのツールを活用するための研修費用も補助対象となる場合があります。2025年度は特にAI活用に重点が置かれています(※2025年5月現在)。
- AIツールのライセンス費用
- クラウドサービスの利用料
- 導入時の初期設定費用
- 操作研修や活用支援の費用
弊社が提供する「AIツール導入+活用研修パッケージ」は、IT導入補助金の対象として認められた実績があります。ツール導入と人材育成を一体的に進めることで、より高い効果が期待できるのです。
中小企業庁の公式サイトによると、補助率は最大1/2で、デジタル化基盤導入枠では最大350万円の補助が受けられます(出典:中小企業庁「IT導入補助金」)。人材開発支援助成金との併用も可能なケースがあり、上手く活用すれば大幅なコスト削減につながります。
中小企業省力化投資補助金の活用方法
中小企業省力化投資補助金は、人手不足対策としてのAI・ロボット導入を支援する制度です。製造業や物流業でのAI活用に特に適しています。DX(デジタルトランスフォーメーション)による生産性向上を目指す企業に最適な制度といえます。
- AI画像認識システムの導入
- 需要予測AIの導入
- 自動化ロボットとAIの連携システム
- これらのシステムを運用するための研修
この補助金は設備投資が中心ですが、その設備を効果的に活用するための研修費用も含めることができます。弊社では、導入するAIシステムに合わせた専門研修を提供しています。
経済産業省の発表によると、補助率は中小企業で1/2、小規模事業者で2/3となっており、最大1,000万円の補助を受けられます(出典:経済産業省「中小企業省力化投資補助金」)。人材育成と設備投資を一体的に進めることで、DX推進の効果を最大化できます。
地方自治体の独自助成金(東京都など)
都道府県や市区町村が独自に実施している助成金制度も活用できます。特に東京都の制度は充実しており、中小企業のAI人材育成を積極的に支援しています。地域活性化や産業競争力強化のため、地方自治体も独自の支援策を打ち出しています。
- スキルアップ助成金(研修費用の一部を助成)
- DX人材リスキリング支援事業
- 中小企業人材育成支援事業
地方自治体の制度は、国の制度と併用できる場合も多く、二重の支援を受けられる可能性があります。弊社は各地域の制度にも精通しており、最適な活用方法をアドバイスしています。
東京都産業労働局によると、「東京都スキルアップ助成金」では研修経費の最大2/3(45万円まで)を助成しており、AI研修も対象となっています(出典:東京都産業労働局「スキルアップ助成金」)。本社所在地や事業所の位置する自治体の制度も確認することをおすすめします。
助成金と補助金の違いと使い分け方
助成金と補助金は似ているようで、実は大きな違いがあります。それぞれの特徴を理解し、適切に使い分けることが重要です。目的や申請タイミングによって、最適な制度が異なります。
- 要件を満たせば原則として受給できる
- 主に厚生労働省が管轄
- 雇用の安定や人材育成が目的
- 事前申請が必須
- 予算枠があり、審査により採択が決まる
- 経済産業省や地方自治体が管轄
- 設備投資や事業革新が目的
- 公募期間が限定的
弊社の経験では、人材育成を主目的とする場合は助成金を、設備投資と一体的に進める場合は補助金を活用するのが効果的です。両者を組み合わせることで、総合的なAI導入戦略を実現できます。
中小企業庁の公式情報によると、補助金は「競争的資金」の性格を持つため、事業計画の内容や独自性が評価の対象となります(出典:中小企業庁「中小企業支援施策」)。一方、助成金は要件さえ満たせば原則支給されるため、計画的な活用が可能です。
人材開発支援助成金に関するよくある質問
AI研修に活用できる各種助成金・補助金について、弊社に寄せられる質問をもとにQ&Aをまとめました。弊社は4,000人以上にAI研修を提供してきた経験から、企業の皆様が疑問に思われるポイントを解説します。助成金活用の参考にしてください。
- AI研修で利用できる助成金にはどのようなものがありますか?
-
AI研修に活用できる代表的な助成金には、厚生労働省の「人材開発支援助成金」があります。この助成金には「事業展開等リスキリング支援コース」「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」などがあり、AI研修の内容や目的に応じて選べます。
研修の目的や企業の状況によって最適なコースが異なりますので、弊社では企業様の状況をヒアリングしたうえで、最も助成率の高いコースをご提案しています。そのほか、経済産業省の「IT導入補助金」や地方自治体独自の助成制度も活用可能です(※2025年5月現在)。
- 人材開発支援助成金の申請手続きの流れを教えてください
-
人材開発支援助成金の申請手続きは、以下の4ステップで進みます。まず、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成します。次に、訓練開始の1ヶ月前までに職業訓練実施計画届を労働局に提出します。
その後、計画に沿って研修を実施し、訓練終了後2ヶ月以内に支給申請書を提出します。特に重要なのは期限の厳守で、1日でも遅れると助成金を受け取れなくなるため注意が必要です。弊社では申請書類の作成サポートも行っています。
- AI研修の費用はどのくらい助成されますか?中小企業と大企業で違いはありますか?
-
AI研修の助成率は、企業規模と選択するコースによって異なります。たとえば事業展開等リスキリング支援コースでは、中小企業は経費の75%、大企業は60%が助成されます(出典:厚生労働省「人材開発支援助成金」)。
賃金助成も中小企業は1時間あたり960円、大企業は480円と差があります。弊社が提供するAI研修(30万円程度)の場合、中小企業なら最大22.5万円の経費助成を受けられることになり、実質負担は大幅に軽減されます。このように中小企業の方が手厚い支援を受けられる仕組みになっています。
- どのようなAI研修が助成金の対象になりますか?対象外となるケースも教えてください
-
助成金の対象となるAI研修は、職務に直接関連する内容で、専門的な知識・技能の習得が目的のものです。具体的には「ChatGPTを活用した業務効率化研修」「AI戦略立案研修」「機械学習モデル開発研修」などが対象となります。
対象外となるのは、趣味や教養としてのAI講座、自己啓発目的の研修、業務との関連性が薄い内容です。また、OFF-JT(職場外訓練)として実施され、10時間以上の訓練時間を確保することも要件となります。弊社のAI研修は、これらの要件を満たすよう設計されています。
- 助成金申請で失敗しないためのポイントは何ですか?
-
助成金申請で失敗しないための最大のポイントは「期限の厳守」と「計画と実施内容の一致」です。特に、訓練実施前の計画届提出は必須で、事後申請は一切認められません。また、計画と実際の内容が大きく異なると不支給となります。
弊社の4,000人以上の研修実績から見えてきたのは、書類の不備が不支給の最大の原因だということです。申請書類のチェックリストを活用し、計算ミスや添付漏れがないか複数人で確認することをおすすめします。また、訓練期間中の解雇等も支給要件違反となるため注意が必要です。
- 助成金と補助金の違いは何ですか?どのように使い分けるべきですか?
-
助成金と補助金の主な違いは、支給条件と管轄省庁です。助成金は要件を満たせば原則として受給でき、主に厚生労働省が管轄する雇用や人材育成に関する支援制度です。事前申請が必須となります。
一方、補助金は予算枠があり審査により採択が決まるもので、主に経済産業省や地方自治体が管轄し、設備投資や事業革新が目的です。弊社の経験では、人材育成を主目的とする場合は助成金を、AIツール導入と一体的に進める場合は補助金を活用するのが効果的です。
- AI研修の助成金申請から支給までどのくらいの期間がかかりますか?
-
AI研修の助成金は、支給申請書の提出から実際の支給までに通常2〜3ヶ月程度かかります(※2025年5月現在)。この期間は申請の混雑状況や書類の不備の有無によって変動することがあります。
申請から支給までの流れは、申請書類の受理、書類審査(1〜2ヶ月)、必要に応じた追加資料の要求、支給・不支給の決定、支給決定通知書の送付、指定口座への振込という順序で進みます。弊社では申請後も労働局からの問い合わせに対応できるよう、サポート体制を整えています。
- 小規模企業でもAI研修の助成金は利用できますか?最低従業員数などの条件はありますか?
-
小規模企業でも助成金は利用可能です。従業員数の最低条件はなく、雇用保険の適用事業所であれば1人でも申請できます。むしろ小規模企業ほど助成率が高く設定されていることが多いです。
重要なのは、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成することです。弊社では従業員10名以下の小規模企業にもAI研修を提供し、助成金申請をサポートしています。小規模企業こそAI活用による業務効率化の恩恵が大きいため、積極的な活用をおすすめします。
まとめ:人材開発支援助成金でAI人材育成を実現しよう
AI研修に助成金を活用すれば、少ない負担で効果的な人材育成が可能です。中小企業なら研修費用の最大75%が助成されるうえ、賃金助成も受けられるため、実質的なコストを大幅に削減できます。
ただし、成功の鍵は「計画性」と「正確性」にあります。訓練開始1ヶ月前までの計画届提出や、研修終了後2ヶ月以内の支給申請といった期限を厳守することが極めて重要です。
弊社では4,000人以上へのAI研修提供を通じて、助成金申請のノウハウを蓄積しています。カリキュラム設計から申請書類の作成まで、トータルでサポートいたします。研修内容も経営層向け、一般従業員向け、IT技術者向けなど、階層別に最適化しています。
「助成金は難しそう」と思われる方も、専門家のサポートがあれば安心です。まずは弊社AI研修サイトをご覧いただき、AI研修と助成金活用についての無料相談をご利用ください。
2025年は国のAI人材育成支援が拡充されています。この機会を逃さず、貴社のAI活用を加速させましょう。弊社の実績ある研修プログラムで、確実に成果を出せるAI人材を育成します。